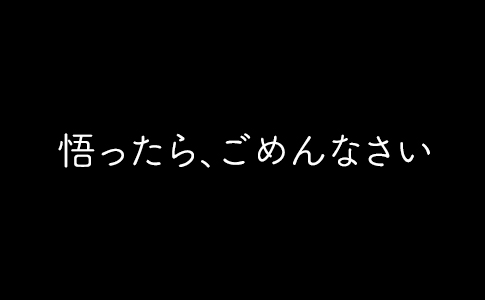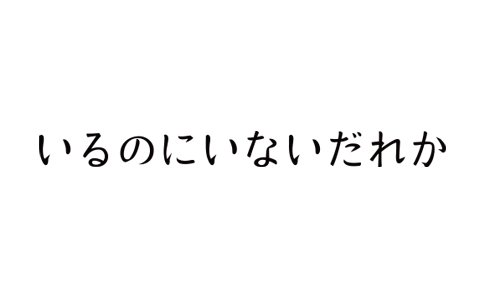「おはよう、タマキ。あのさ、今日の予定はあるの?」とその後には何かの誘いがある前置きの電話越しのカオルに向かって私は本棚から取り出そうとしていた長久允の『ウィーアーリトルゾンビーズ』を一旦もとに戻しながら「うん、今からちょうど、パラドックスへ朝ごはんを食べに行くとこ」とわざとそっけない口調で返した。
「そう、よかった。っていうのは、僕も行きたいなって思ってるんだけど、ほら、雨強いからさ、バスと自転車じゃちょっとと迷ったんだけど、もしタマキも行くのなら、乗せていってもらえないかなと思って」「いいよ。じゃあ、今からうち、出るから」と車に急いだ。
ワイパーの規則的な動作音とまばらな車内に響く雨音に紛れながら「フォーエバー、フォーエバー」と念仏みたいに小さく唱えてみる。
カオルの家の前に車を寄せると、カオルよりも先にアキが助手席に飛び乗ってきて、続いてカオルが後部座席に着いた。
「おはよう」を言い合い終えたあとアキから「昨日の夜ね、仕事の帰りにカオルの家に寄ったら、そのまま寝ちゃって。朝、何をしようかカオルと話してて、タマキがもしかしたらパラドックス?だっけ?に行くかもって話になって」と嬉々とした表情と語調で説明があったから「それなら、最初からアキがいるよって言ってくれれば、もっと急いで来たのに」と私がアキとカオルに交互に視線を向けると「だって、ちょっと驚かせたいじゃない。きっとタマキは喜ぶだろうと思ったから」とアキと私の間から顔を突き出して言うカオルはうれしそうだ。私は何と返せばいのかわからなくて「ありがとう」とだけつぶやいて発車させた。
<臨時休業 SORRY!>と黒のマジックで書かれた張り紙が、パラドックスの店のドア中央に貼られているのを私たちは雨に濡れながら注目した。
カオルがまず「そっかあ」と現実を受け入れた感じで言う。なみなみと注がれたコーヒーをすすりながら、メープルシロップが滴るコーンミールパンケーキとテンペと野菜の炒めもので満たされる準備万端で来ていた私は、落胆で思考が停止したところで、アキが「あー、がっかりー。今日こそふたりのお気に入りの店で朝ごはんを食べられると思ったのに」と私が知っている「がっかり」とは程遠い調子でドアにへばりつき拳でドアを叩きながら叫んだ。あまりのオーバーな言動がおかしくてカオルと私は背後で笑うしかないし、なんとなく次の展開を予期していた。
「っていうことはよ、他に行くチャンスができたってことよ」と言ったかと思うと、くるりと身体をひっくり返し、すでに歩き始めたアキの後ろ姿に向かって「どこか他にあるの?」とカオルが訊くと、「うん、ちょっと」と言って振り向くことなく車へ向かうから、カオルと私は後を追った。
私たちは、アキが以前人から聞いて気になっていたというベトナム料理店へ向かうことになった。店の隣にある寺の土曜の朝の読経を終えた人たちが主に利用するためにフォーが朝から食べられるらしい。フォーフォーうるさい助手席のアキとルームミラーに映る、手を後頭部で組んで外を眺めているカオルを乗せて私は車を走らせながら、予定は狂うくらいがちょうどいい、と思えていた。
こじんまりとした店には、すでに何組かのお客がいてフォーをすすっている。店内にはフォーの香りと湯気が立ち込めていて、それだけでも気持ちがほぐれる。ほがらかな表情の小柄な男性が私たちのテーブルにお茶を持ってきて、朝のメニューは1つだから注文は3人前でいいかどうかを確認し、厨房へと戻っていった。
「朝フォーだなんて、楽しみー」と声と肩を弾ませ私の隣で言うアキが厨房の方に目線を向けたので私もつられて向けた。あ、と私が言うよりも先に、わ、と言いながら席を離れ厨房へと早足で向かったのはアキだ。私は見開いてしまった目のまま、前にいるカオルに顔を向けると、カオルも眉毛を上げていた。厨房にいるのは「白い彼女」だ。「なぜ」が私の頭の中でいくつも飛び交う。
厨房と客席ホールの見えない境界線ギリギリのところで両手と身体で壁に寄りかかり、厨房に向かってアキは話しているようだったが、雨音や店内BGM、厨房の音で断片的にしか聞こえない。私だって行けばいいだけなのに、こういう時の潔さがない。かと思っていると、アキは向こう側に手をやんわりと振ってから席に戻ってくるなり、テーブルに両前腕を置いて前のめりで「イオはね、ここで働いているんだって」と言ったから、「どう見たって働いてるでしょ」と突っ込みたかったのを省略して「イオっていうのは、彼女のこと?」と私が確認のために問うと「あ、そう、彼女の名前。イオはね、そこが家でもあるみたい」と言いながら寺のある方を一瞬指さした。私は半ば反射的にイオの生活とあの夜に見た腕の無数の傷を関連づけようとする思考が起動したので途中で阻止。無意味だ。
何の判断もしてなさそうなカオルがただうなずいているのをちらっと見て、私は厨房で手元と周囲へ交互に目線を向けるイオの姿を眺めていると、おしぼりで手を拭きながらアキが「それでね、イオと今夜のオープンマイクで会う約束したから。もともと行く予定だったみたいよ」と得意げに言うと「やっぱり」と両手で包んだ湯呑に目線を落としたままカオルは言った。「やっぱり?」と困惑した私はそっちのけで、カオルとアキは笑い合っているけど、悪い気はしない。
待ってました!のタイミングで運ばれてきたフォーの湯気が私たちの間を立ち込める。テーブルの中央には別盛りのどっさりパクチーが置かれ、その香りで私はむせた。私はパクチーが食べられない。