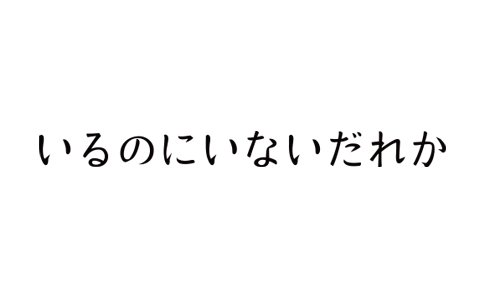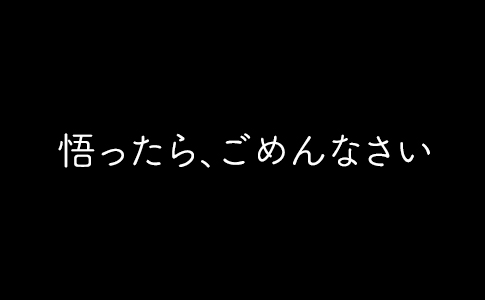結局いつものようにカオルと別れてから、私は帰り道を左折するところを右折したり、まっすぐ行くところを左折したりして遠まわりをすることにした。暗闇の中の連なる人工的な光を、ただひたすら追い越していくと集中がより絞られる。適当に流したままのカーステレオから流れてくる曲の音量を上げる。腕と足首の一定の運動が気持ちのバランスを整えてくれるようで、いつまでもどこまでも行ってしまいそうだった。
今夜のハイライトが始まる。
数時間前のマイクの前に立っていたところから見ていた光景が表れて、カオルの表情、それに付随して彼と交わした言葉、結局来なかったアキやイオのことも思い出して、何に対してなのかわからない苛立ちも湧き上がってきてアクセルを押す右足に力が入る。
「私が猫だったとき」と押し殺すような声でつぶやいたと同時に、普段は思い出すこともない過去の映像や考え、感情が表れて次を引っ張り出してきては消えていく。自分の意思を無視して記憶やそれから派生するものが発現してきて、内側ではもう抱えきれなくなっていた。いずれの目的地であった自宅を現在の目的地に切り替えてハンドルを握り直し、背筋を伸ばした。
部屋に戻った私は急いで机の引き出しからペンとノートを取り出し、言葉を綴った。とにかく出てくるがままに書き続けた。何かが外側に向かって流れていくようだった。
もう今は、カリンの実が落下する音で起こされることはない。まだ枝に残っているわずかな黄色い葉が揺れているのが洗面所の窓から見える。数日の内にはすべて落ちてどこかへ行ってしまうだろう。その代わりなのか、それとも私がカリンの音を贔屓していただけなのかは分からないけれど、いつからか、まだ薄暗い朝の時刻に屋根の板に硬いものが触れ合う音が聞こえてくるようになっていた。軽快でリズミカル。音の重みから、カラスだろうと寝ぼけながら確信している。
土曜日の店内はもうすでに朝を過ごす客でごった返していて、甘い香ばしい匂いが充満しているから無条件で肩の力が抜ける。ジャケットに付いていた水滴を払い落とした後、店の奥へと進む私に、いつもの店員が「おはよう、いらっしゃい」と声を掛け、忙しそうにカウンタ―席の客にコーヒーを注いでいた。
「もう僕は注文したから。もしかしたら、これからアキが来るかも」と言いながらカオルが渡してくれたメニューを広げ、一通り眺めてからコーンミールパンケーキとコーヒーを頼むと、すぐにコーヒーが運ばれてきて、カオルはついでにおかわりを注いでもらっていた。ふたつの湯気がなびく。
少し先に運ばれてきたパンケーキを食べ始めたカオルを追うように、私も後から食べる。メープルシロップのピッチャーもテーブルの上の同じ線を行ったり来たり。アキはまだだろうか。いや、アキのことだから、途中まで来て、フォーを食べに行ってしまったかもしれない。そしたらアキはイオにも会うのかな。
「そうだ」と途端に言ったカオルは、ナイフとフォークを皿の上に置いて、何やらガサゴサと自分のバックパックの中を漁りはじめた。なんだろう、ここでチョコレート登場か、と切り分けたパンケーキを口に運びながら眺めていると、新聞紙で歪な球体になった物を私の皿の左側に置いた。
「何これ」と言いながら私はナイフとフォークを置いてから皿をずらしてその球体を目の前に置いて、カオルと交互にみつめると、「プレゼント」とだけ目を見開いたカオルが返してきた。プレゼント?怪しい。私は新聞紙の塊を両手の2本指でつまみながら、ゆっくり開いていく。中から出てきたのは、拳ほどの大きさの木彫りの猫の置物だった。アジアの屋台のお土産コーナーにある、どこにでも売られているようなものだったが、鼻や耳の辺りは少し削れていて年季の入った独特な雰囲気を醸し出していた。切れ長の目がいい。
「昨日ね、リサイクルストアに行ったら、ちょうどあって。あ、タマキだって思ってさ」と得意げな笑みを浮かべながら言う。私はその小さな猫をうずもれていた新聞紙から取り出し全体を見回すと、お尻のところには<300円>と書かれた緑色の丸シールが貼ってあった。カオルは「あっ」と言って手を伸ばしてきたが、私は「いい、このままで」と言って、小さいそれを素早く引き寄せた。パンケーキに顔を突っ伏したい。
空腹が満たされ、まだ残っていた2杯目のコーヒーを飲み干して、私はジャケットを着てマフラーを巻き始める。まだ湿っていたが、今も外は雨だ、どうせまた濡れる。
「タマキ、行くの?」
フリーペーパーを読んでいたカオルが、立ち上がった私を見上げる。
「うん、行ってみる。アキが来たらよろしく言っておいて」
「うん、言っとくよ。じゃあ」
「じゃあ、またね。猫、ありがとう、部屋に飾るよ、魔除けになりそう」
「魔除けか。まあ、それもいいかもね」
私は新聞紙で包み直した猫を抱えながらレジで会計を済ませ店を出た。温まりきった身体に湿った冷たい空気が貼り付いて気持ちいい。店の正面のガラスに書かれた店名『PARADOX』越しに、フリーペーパーを読むカオルを見る。カオルの今には、もうすでに私はいないことを横目で確認をして新聞紙の塊を腹の辺りに押し当て、駐車場の車へと向かって走った。
終わり