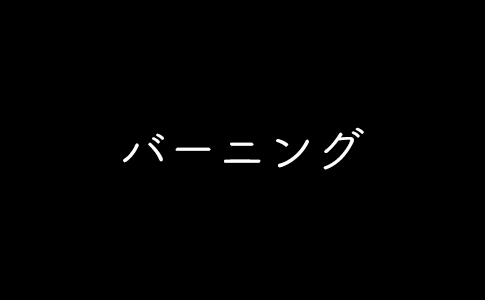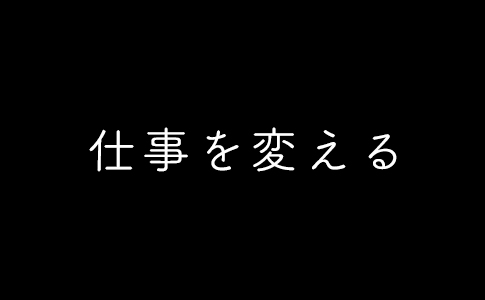しとしと雨が降っている。この街では雨は日常的で、降ったり止んだりしているから、傘を持ち歩く人は少ない。濡れてしまっても気にしないのが常だ。今も、手ぶらで道を行く人が通り過ぎて行った。歩道の隅っこや木の根元を囲み、円陣を組んでいるような葉っぱも水に覆われ、放っている黄色も鮮やかになるから嬉しい。
私は今、家から車で1時間ほどのカフェの一番奥にある4名用のボックス席に座って、椅子の薄緑色のビニールシートと、アイボリーの壁が交わる所に収まるように、身体全体をその角に預けている。
いつもの場所に来て、いつもの席に着いて、一旦はメニューを眺めて迷ったふりをして、いつものホットコーヒーとコーンミールのパンケーキと野菜とテンペの炒め物のセットを注文して、いつものペースで過ごすのが、私の何よりの自分の時間だ。安穏と静かに、決してはみ出すことなく生きていくのが、今の私には正しいのだ。だからこそ、今朝のように普段通りに雨が降ってくれているのは気持ちが落ち着くのでありがたい。おかげで読書がはかどるってものだ。
今朝は、この場所でこの時に読むと決めていた須賀敦子の『須賀敦子の手紙』を愛用の黄色のリネンのトートバッグに忍ばせている。早速読もうと、椅子の右側に置いた少し湿気たバッグに右手を潜らせて左右に動かしていると、お守りとして日常的に持ち歩いている鹿子裕文の『ブードゥーラウンジ』の表紙絵がちらっと見えた。「あるな」と確認。この本の購入時におまけでついてきた三輪車に乗る鹿子さんのポラロイド写真のことを、連鎖的に思い出してしまう。
先に運ばれてきたコーヒーを早速一口飲んで、大きく息を吐き、放り投げられた人形のように、再度、角に寄りかかり、いつもの風景を見渡す。カウンターには、何度かこの店で見かけたことのある常連と思われる年配の男性が新聞を広げている。ガラスの壁沿いのテーブル席には、何やら書き物をしている女性がいて、その反対側のガラス壁沿いの席では男性が本を読んでいる。
それぞれの小さな選択がこの場に今居ることにつながっている。顔の見える範囲の距離に居る。けれど、また恐らく数10分後にはどこかへと散っていくだろう。そしてまた近づくこともあるかもしれない。まるで、自分がハンドルを握っている遊園地にあるコーヒーカップのようだなと思った。思い思いにハンドルを回すけれど、時にはコントロールが不可能になるから、本当は怖いくせに楽しんでいるふりをした悲鳴を上げることもあるだろう。その平面上での一瞬の接近が幾度かあると、互いを「あの人だ」と認識し始めるのかもしれない。
再度、今目の前にある、その一瞬というやつをぼんやり確認して、また外へと視線をやる。雨脚が、やや強くなってきたようだ。そして少し焦点を引き、ガラス壁に描かれている店名にピントが合う。雨水が垂れて、ゴールドに黒で淵取りされた文字が少し歪んで見える。
「見える」のであって、実際はちっとも歪んでいないのかもしれない。歪んでいるのは、自分の思考の方なんじゃないの?あーあ、歪んでいるのは結局自分。こんな私なら、いっそのこと消えてしまってさ、だって、誰も困らないでしょ、私が今いなくなっても。変わらず、この日常は平常通り通過していくのだろうから。もし、消えることはできなくても、せめて無色透明にはなれないだろうか、と意見する。いや、もしかしたら、私は既に無色透明になっているのかもしれない。だって、この空間にいる人たちは、私のことを「あの人だ」と認識しているはずなのに、一切私に目線を向けることはないし、声も掛けてこない。そういうことか!と両手の拳を太ももの上で強く握るポーズを決め、無意識のうちにニヤついてしまった。あ、しまった、誰かに見られて気持ち悪い奴だと思われたらどうしよう、と瞬時に緊張の電流を口元に流し、あなたが見たものは勘違いですよ、誤解しないでくださいねと、ごまかすために能面みたいな顔をして、姿勢を整えるふりをした。ん、でも、そもそも私は無色透明なのだから、気にする必要なかったんだ。あははははは。
「コーヒーのおかわり、いかがですか」と店員に声を掛けられ、私は冷静さを装って
「お願いします」と咄嗟に返した。
残念、まだ色あるものとして存在していた。そろそろコーヒーのおかわりがほしそうな存在として居ることが証明されてしまった。
「はいどうぞ。ごゆっくり」2杯目のコーヒーをなみなみと注いだカップを私の左前に戻し、軽い笑顔を残して、他の客へと向かった。
「ありがとうございます」と、私は口だけの笑顔といっしょに返して早速コーヒーをすすり、何かから逃げるように、目の前にある本へと目線を戻した。
すると視界の左斜め上の方から、右下に向かって動いてくる青い塊が滑り込んできて、真ん中当たりで止まった。私は顔を上げ焦点をその塊に合わせようとしたが、それより先に、私の鼓膜に「おはよう」という音が鳴り響いた。