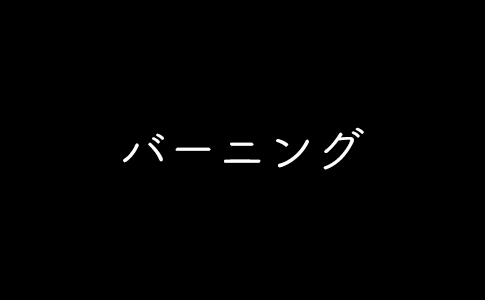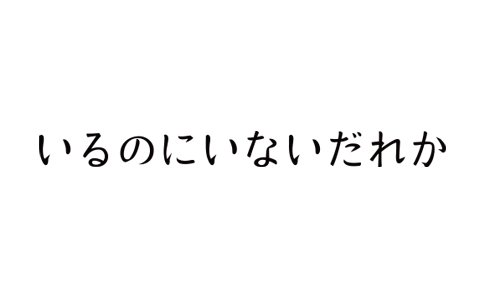まばたきを終えると、目の前の青い塊の解像度が上がった。
カオルだ。「おはよう」と返しながら前かがみになっていた体全体を私はもたげた。
カオルは、青いジャケットとそのフードを脱ぎ、水滴を払い落とし、彼の左側に丸めて置いた。そして、白地にオレンジの糸で花が刺繍されたニット帽を脱いでジャケットの上に置いた。帽子を外した勢いのおかげで、くせ毛がさらにうねりを増しているのを彼は認識しているのだろうか。
このあたりは雪になることはほとんどないが、2月の雨はさすがに冷たい。今朝もいつものようにバス停から自転車に乗ってきた彼の鼻先が赤く光っていた。「鼻、赤いよ」と私が言うと、何を思い浮かべているのか気づいたのだろう、彼は無表情な目をして両口角を左右の端へ思い切り引き寄せた。それはほんの一瞬の笑み。さっきコーヒーのおかわりを注いでくれた店員へ返した私の顔もこんな感じだったのだろうな、と少し懺悔した。彼は店員へ早速注文をしたようだった。その映像だけは覚えている。
カオルとは、この店で半年程前の夏に知り合った。以前からこの店で本を読んでいるのは何度か見かけたことはあったが、話したことはなかった。ま、当然だけど。しかし、ある日、店内が満席状態のときに彼が来店し、私は座っていた定位置の4人用のボックス席を譲って帰ろうとしたが、結局は相席をすることになったのだ。同じ長テーブルの対角線上に、それぞれの本やノート、ペン、朝ごはんを広げ、それぞれの時間を過ごすのは、安心安全が保証されたもので居心地が良かった。
その日をきっかけに、この店に来るタイミングが重なったときは挨拶や話をするようになった。好きな音楽や映画、本、本屋も似通っていること。実は彼と私は同じ街に住んでいて、この店へ彼も本を読むために、行きのやや登り路はバスに自転車を積んでやってきて、帰りは寄り道をしながら自転車に乗って下るということを知った。そんなこんなで、居合わせたときは、今では向き合って座るのが日常。
と、いうのは、私とカオルの間の「私たちのはなし」で、私側はちがう。
私は、彼のことを1年半程前から知っていた。行きつけの本屋で歩き回っていた際、ある1人とすれ違って瞬時に私は振り返って、ピースマークの缶バッチが付いた黒のナイロンのバックパックを背負った長身が遠ざかっていくのを凝視していた。周囲には他にも客はいたのに、だ。決して容姿に一目惚れというわけでも、着ていた「I ♡」のTシャツがかわいかったわけでもなく(いや、実際、とても似合っていた)、なんというか、匂う、というのに近かった。
その後、同じ本屋やリサイクルショップ、食料品店でも見かけることがあって、目で追ったり背後を通り過ぎたときには、鼻をすすって特定の匂いがするのか確認をした。匂いはなかった。その人物が、カオルだ。だから、生活圏を少し離れたこの店で見かけたときは、極力会いたくない知人と行先で出くわしてしまったときのように、反射的に身体をよじって顔を隠した、必要もないのに。
私は、彼にはこのことを話していない。今後も話すつもりはない。だから、私たちの間には認識している事実が異なり続ける。もしかしたら、彼側の事実もあるかもしれない、私が知らない、見ていないだけで。そうやって私たちは事実の一部分(大抵は、自分にとって都合のいいもの)だけをそぎ落として、その断片を自分の脳みそに押し当て馴染ませる。せっせせっせと粘土創作の作業のように。その創作物はぶくぶくと大きくなる。
朝ごはんが目の前に置かれた。開いたままだった本を閉じ、バッグにしまっている間に、彼の朝ごはんも運ばれてきた。私たちは儀式めいて背筋を伸ばし顎を引き、胸の前に蕾のような合掌を携えた。おいしい、が保証された匂いが立ち込める領域を挟んで、私たちは目を一瞬合わせた。「いただきます」と言いながら、ゆっくりとおじぎ。これは、もともと私がしていたものを彼がまねて習慣化したもの。
私は先にテーブルの端の真ん中に置かれたメープルシロップのピッチャーを握り、自分のコーンミールパンケーキに大きな光る円を1つ描いた。彼が次を待っていることを気にして私が急いでいるのを察されないように、ゆっくりとピッチャーを元の位置よりやや彼寄りの所に置いた。すぐに彼はピッチャーを持ち上げ、自分のコーンミールパンケーキに細かいジグザグを描いてピッチャーを元の位置に戻した。気が変わって、もう少し甘味を欲したふりをして、私はもう一度ピッチャーを握り、円を描いて戻した。すると、彼が再びピッチャーを握り、ジグザグを描いて戻した。私も再びピッチャーを引き寄せ、戻した。彼も再び引き寄せ、戻した。
これは!
私はこのときあたりから、私たちは『君とボクとの虹色の世界』を再現していることを確信した。次第に単純化され、一定のリズムが守られた動作を止めるわけにはいかなかった。行ったり来たり。行ったり来たり。「フォーエバー」私たちは吐くように叫んだ。