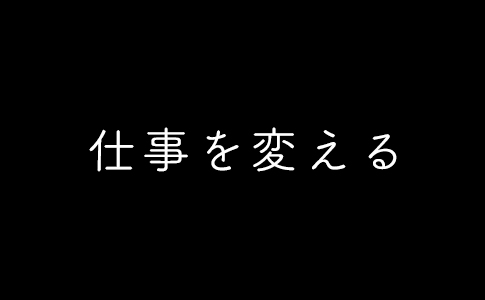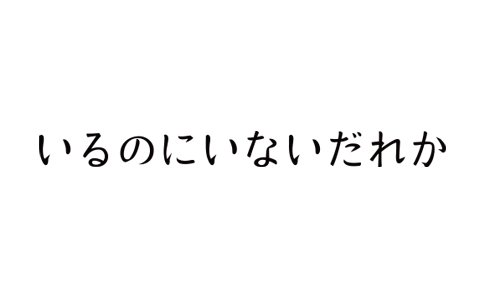私は前かがみの体勢のまま上瞼をぐっと引き寄せてカオルの目を見た。カオルも私の目を見ていた。了解。まばたき。
私は、ゆっくりゆっくりと背筋を伸ばし、メープルシロップのピッチャーを掴んだり離したりしていた左手を一旦ひざ元へ引き寄せた。そうしてから自分の目の前とカオルの前に置かれた朝ごはんを交互に眺めながら、フォークとナイフを手に取った。
今朝はふたりともメープルシロップをかけすぎたから、やたらにパンケーキがつやつや光っているのは同じ。ちがうのは、私のテンペのそれが、カオルは厚揚げだ。なぜ、いつものテンペでなくて厚揚げなのだろうと疑問がわくと、厚揚げの白さがやけに際立って見えた。
「カオル、今朝は厚揚げなんだね」
「うん、タマキはいつも通りのテンペなんだね」
「うん、ちがうメニューにしようか迷ったんだけど、結局いつものになっちゃうんだよね」
「そっか、でも、ほんとは最初から何を注文するかは決まっていたんじゃないのかな、ほら、迷うって、ちょっと楽しいから」
「え、じゃあ、カオルは今朝は最初からいつもと違う厚揚げにしようって決めてたってこと?」
「いや、決めてたわけじゃないけど、今朝は厚揚げだなってメニュー見て咄嗟に思っただけ」
私は口の中に入れたばかりのテンペのせいで発話ができないことをいいことに、大げさにただ頷くだけにした。ほんとは、今朝は厚揚げと迷うことなく選択した心境の変化を問い詰めたかったが、その欲望は唾液と混ざり合ったテンペといっしょに飲み込むことにした。ちゃんと消化してくれよ、頼むから、と祈りながら。
しばらく食べることに集中していたが、だんだんと口に朝ごはんを運ぶ間の間隔も広がるように、他の欲求への意識も広がってきた。
カオルは毎週水曜日に発刊される、街の情報が載っているフリーペーパーを、足元に置いていた黒のバックパックから取り出し、イベント情報欄をチェックしていた。特に音楽ライブイベントに関しては入念だ。私は、須賀敦子の本の続きを読んだり、その中で気になった言葉や文章を書き留めたり、時折は外や店内の風景を眺めて意識を移動させるのを繰り返してた。そして、3杯目のコーヒーの最後の一口を飲み干して私は言った。
「そろそろ私、行くね」
「そっか、僕はもう少しここで過ごしていくよ」
「うん、帰り道、雨が降ってるから気を付けて」
「ありがと。タマキも運転、気をつけて。じゃあ、また」
「じゃあ、またね」
立ち上がった私を見上げたカオルの眼差しを焼き付けてレジへと颯爽と向かった。自分の分の支払いを済ませ、カオルの後ろ姿を見たい気持ちと取っ組み合いながら店を出た。店の前に置かれたカオルの自転車に質問した、「じゃあ、また」の「また」って一体いつだよ、と。
降り続く雨の中、私は自宅へと車を走らせた。ワイパーの動く音とタイヤが水を弾く音で、せっかくの音楽もかき消されてしまう時があるけれど、霧掛かった薄暗い灰色の景色の中を通り抜けていくのにはちょうどよかった。角のとんがった情報の輪郭が曖昧になってくれたくらいの方が落ち着く。
すれちがう車に乗車している人の表情を見て、その人らの今の状況について想像をするのが好きだから、私は今日もそれを。
誰にも見られていないと油断をしている間抜けな顔、眉間にしわを寄せている顔、助手席にいる相手と穏やかに笑い合っている顔。世の人生のハイライト。一番近い存在である自分から離れることも、誰かの視線から世界を見ることは決して出来ないとしても、ほんの一瞬、全く関わりのない人の人生に紛れ込めたような気持ちになれる。今日は、雨のせいでどんな顔もいびつだから、どんな状況なのかは想像しづらいけれど、余計なお世話だとは思いながらも、接近した1台1台の世界に、精一杯の「はじめまして」と「お元気で、よい人生を!」の挨拶を送らずにはいられない。その瞬間、たまたま大接近をして、離れる。もう二度とすれ違うことはないのかもしれない。まるで…って1時間くらい前も同じこと考えていたなと気づいたので、それ以上頭の中でセリフを続けるのは止める。
対向車が続くと、そのタイヤ音のリズムに乗って、忙しい挨拶に集中できていたのだが、車が途切れるとカオルのことが浮かび始めた。今頃、お気に入りの場所を自転車で通過しているのだろうか、いや、もしかしたら、誰かに会いに行っているかもしれない、と頭の中でぶつぶつが止まらず、自分の足が絡まったように転倒。はい、さっきまでの微笑み凱旋パレードは終了。
赤信号で車を停車させ、右ひじをドアと窓の交わる出っ張った丸みのある部分に引っ掛けて、さらに右頬を掌に引っ掛け息を吐いた。そしてまた吸って、今度は意識的に細く長く息を吐いた。車の中で流れていたデス・キャブ・フォー・キューティーの『ラック・オブ・カラー』に、ワイパーの動くリズムが微妙にずれながら混ざっているのを、まばたきをするのも忘れ、聴いていた。