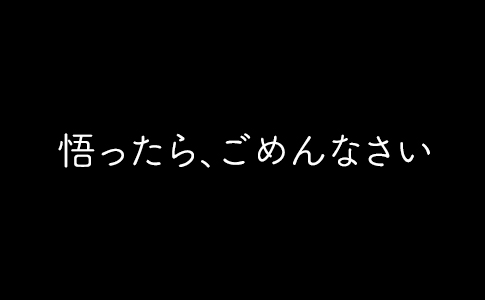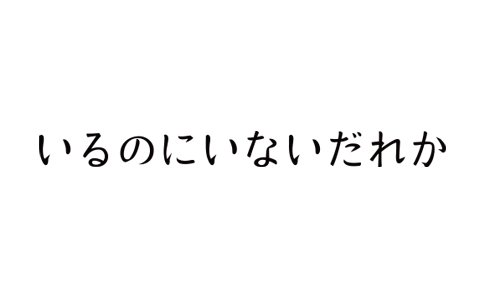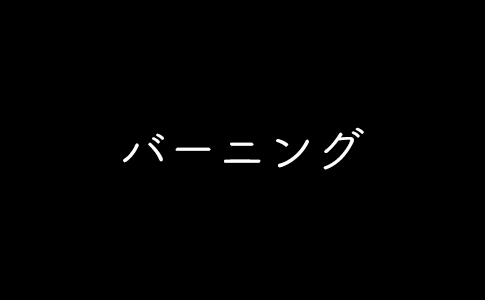洗顔を終えて、タオルで顔をぬぐいながら、洗面所の窓からとなりの家のかりんの木を見上げる。こぶし大くらいの、薄緑色の実が順調に育っている模様。昨年より数は多いような気がする。
朝の空気感、特に今朝のような雨の降るときの変化に夏の終焉を感じながら、使っていたタオルを洗面台の隣にある洗濯機に放り投げ、他に洗濯物がないか、回収のために家の中をうろついた。そろそろ、羽織れる薄手の長袖も収納ケースから出して洗濯をしておいたほうがいいかもしれない。
夏が終わろうとする兆しがあると、なぜだか、何をしたか、どんな思い出や特別なことができたのかを振り返って数えてしまう。
私の今年の夏は、昨年と明らかにちがったのは、私の時間にオレンジがいなくて、カオルとアキ、そして「白い彼女」がいること。何度かオープンマイクに行ってみたが、「白い彼女」はあの日以来見かけることがなかった。けれど彼女の存在が私の内面で薄れることはなかった。暑くなり始めたころは、収納ケースから出した夏服には、オレンジの毛がたくさん付いていて、私は泣きながらそれをせっせと飲み込む儀式を続けていた。
カオルとは、互いに仕事が終わった夜に会う頻度も多くなっていたような気がする。カオルが探したライブや他の会場のオープンマイクに行って、その後はカオルか私の家で、借りてきたDVDで映画を観て、そのまま寝落ちるなんてことがパターンだった。その流れの中に、時折、アキも加わることもあった。私たちが「寝落ちる」のは文字通りの眠りに落ちるのであって、身体が交わることはなかった、2人であっても3人であっても。
ある8月の夜、アキが観たいと言った『ロスト イン トランスレーション』の映画をカオルの家で3人で観ていたのだが、アキは疲れていたのか、途中で眠ってしまっていた。映画が終わって、カオルと私はそのまま添い寝をしていた。私はやがて聞こえてきたカオルの寝息を数えていた。すると、何か物音がして私は目を薄ら開けると、アキが目を覚まして立ち上がろうとしているところだった。
「アキ」私は小さく声をかけた。
「あ、タマキ、ごめんね、起こしちゃったね」
「いいよ、私も寝付けないでいたところだったから」
「そっか。ねえ、映画、面白かった?」
アキと私は、カオルを起こさないように、そっと部屋を出て、涼みに玄関先のポーチに腰を下ろし、微かな夜風に当たりながら、私はさっき観た映画の説明をした。それから互いの好きな映画やシーン、俳優の話で盛り上がった。アキとのおしゃべりはいつでも楽しく尽きることがない。そんな中、アキが言った。
「ねえ、タマキ。タマキとカオルって、付き合ってるの?」
私はとたんに目が覚めて背筋に力が入った。弟が聞くことなんですかね、それ。
「いや …付き合って…ない…と思う」
「でも、セックスはした?」
「してないよ、まさか」
「そうなんだ。じゃあ『ベスト フレンド フォーエバー』みたいなってこと?」
「それだね、それ」
私たちは自分たちのやりとりのあまりの軽快さに、声を控えるかわりに肩を大きくゆすりながら笑った。そして、アキは横目で私の表情を確認するように見つめた後、ゆっくりと私の左肩に彼の頭を傾け、ため息のような細くて長い息を吐いた。私もつられて長く息を吐きながら、彼の頭に左頬を寄せた。私たちは、しばらく無言のまま座っていたが、やがて眠たくなってきたので部屋に戻って、それぞれ横になった。
アキは、私のカオルへの感情に気づいているのだろう。私だって、望んでないと言ったら嘘になるが、自分は相手の奥の方に踏み込みたいくせに、相手には踏み込んでほしくないというズルさがあるから、今がちょうどいいんだ、完璧なんだと、私は自分に言い聞かせている。足るを知る。知ってくれ。
私は、作動終了を告げる音が鳴った洗濯機の蓋を開け、渦巻いてドラムにへばりついた衣服を引き上げ、その濡れて重たい塊をほぐしながら、アキとのその夜のことを思い出していた。
「ベスト フレンド フォーエバー」
思わずつぶやくと、その言葉の薄さと軽さに笑いをこばさずにはいられない。アキのセンスに一礼したい。
室内物干し台に洗濯物を干し終え、それに扇風機の風をあて、先ほどまで干されていたグレーと黄色のボーダーTシャツに腕を通し、デニムのパンツをはく。まだ足は冷えないだろう、と靴下は却下。
台所のシンクに置かれたままの、白湯を飲み干した後のカップを洗った後、お守り本はすでに入れてある巾着袋を持って本棚に向かう。今朝は何を読もうか。目でタイトルを追う。