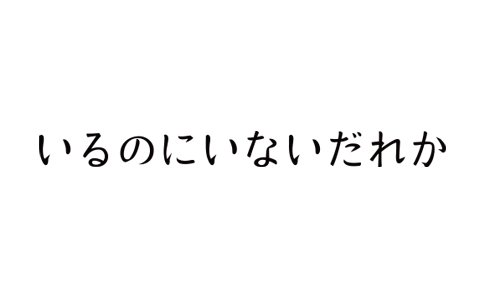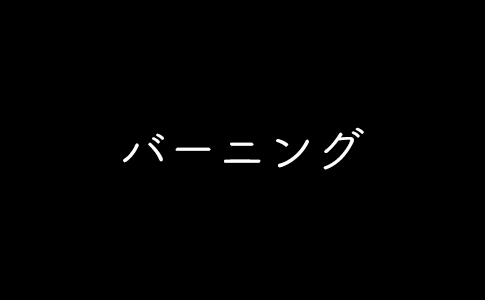どのくらいの時間が過ぎていったのかはわからないけれど、少なくとも私のなかでは待っている人の中に苛立ちや何か異常な事態になった心配を生じさせる時間は経っていたのではないかと不安になって、そのまま立っていた。部屋の小さなオレンジ色の照明さえも私に対して向けられているようで、一層、問い詰められているような焦りを感じていた。
そんな自意識過剰な妄想圧に追い出されて、ところ天式に私の口からは滑らかに「私が」と言葉が出てきていたのに「が」の母音「あ」の余韻あたりで気づく。にょろっと出てきたところ天は、途中で止まって受け皿に届かぬ高さで、宙で、うなだれたままだ。
私は意識的に息を強く吐きながら、カオルや私、他の人がいる部屋の隣のやや薄暗くなった玄関に通ずるホールに目をやり、アキやイオが「間に合ってよかったー」と言って安堵の笑みを浮かべて立っている姿を探したが、もちろんそんなはずはなく。ここにいることを選ばなかったアキとイオのことを思い、目を閉じた。
映像としての情報が入ってくるのが閉ざされたからか、脳内を飛び交う思考のうるささに、今度はビビリおののく。でも、とにかく、と私は思考のひとつひとつを、ババ抜き用にトランプを、もしくは麻雀の牌を、ゲームを開始する前のように両手で大きく円を交互に描くようにして混ぜ合わせる。そのひとつひとつの感触を手の指や掌で感じながらも、絵柄の細部や微細な原料や成分を知る能力はない。あったら面倒だ。そして、よく混ぜ合わせたら、やがてひとつにまとめたり、並べたり、配ったりするんだ。
思考について思考していたら、うとうと気持ちよくなってきて、右斜め前に重心が傾き「あっ」と反射的に声が出て目を開けた。あわいの中に浮遊していると、その中のひとつがつまみ出され、自動操縦的に言葉という形へと転換されてきた。
「私が……猫だったとき……」自分で発した言葉や音の振動が私全体に伝播して、無機質的に、機械的に、さらに次のひとつがつままれて私を発動させた。「……ねむたかった」と、とろみのあるこぼしかたをすると、私の左斜め前に座っている最後の演者であった腹話術をした人が肩を小刻みに震わせ、右手の指先で口元を軽く押さえ、笑っているのが分かった。
「ときどきはコーヒーを飲んで、街にでかけたり、草むらの中でバッタやスズメも狙った」と言ってから、私と平行している部屋の壁についた染みに焦点を合わせていた視線をカオルにほぼ全部向けた。眠気も焦りも不安もなくなっていた私は「そして家に帰って、おでこを、だれかの胸元にあてて、心臓の鼓動を感じて、眠ったふりをして、だれかの胸元にそえた右手の爪を立てたり、本気で祈ったりしたんだよ」と続けた。最後の「だよ」には、投石するかのように語気を強めていたのを知っているのは、きっと私くらいだろう。気づかれてしまうのはダサい。
私は次のひとつが拾い上げられる前に合掌をして頭をゆっくり下げ、私を見つめているカオルには気づいていないフリをして、カオルのとなりに戻った。私は背を丸め、両足を前方へ突き出して、ふうっと息を吐いたら、何だかおかしくなってきて、鼻で笑っていた。
冬の夜はさすがに冷える。車の中も冷凍庫のようで、吐く息も綿菓子みたいにふわふわ白い。エンジンをかけ、オンにした暖房に「頼むよー」「早くー」と、カオルと私は声を張り上げて両肩を上げたり下げたりしていた。走り出して数分後には、暖気が足元や上半身に届いて心身がほぐれていて、今夜の演者について話している時間に、私が予期せずマイクの前に立ち吐露したことは、まぼろしだったかのように、カオルも私も一切触れなかった。私はわざとだけど。
さっきまでの寒さを忘れてきた頃、カオルの家の前の路肩にゆっくり車を寄せ、縁石と車道が作る角にまとまった落ち葉を踏みつける、硬くて軽い音の束が車内に響いた。楽しい時間が終わる合図だ。私がサイドブレーキをかける頃には、カオルはシートベルトを外し、何のためらいもなくドアを開け、颯爽と「じゃ、ありがと、またね」とか言いながら外へ出て行ってしまうのが毎度のことだが、シートベルトは外したものの、今は助手席に座ったまま前方を見つめていて街灯に照らされていた。鼻からは綿菓子。
やがてカオルが「知らなかった」と言いながら、私の方へ視線を向けてきた。私は戸惑いながらも、若干カオルが「タマキの自分に対する気持ちに」と続けてくることを期待し、でもそれがにじみ出てしまわないように、軽さと平静さを保って「なにを?」と返してやった。
カオルは姿勢を改め、「タマキが前は猫だったってこと」とすごい真顔で言った。私の全身の逆立っていた毛は、たちまちに、しんなりとしたのを感じて、私もすごい真顔で、でもほんの少し眉間に力を入れて「そりゃそうだよ、だって、言ってないし」と口をやや尖らせながら返し、前方に見える暗がりの中の住宅街を見つめ、車のヘッドライトを落とした。カオルと私は、こらえきれず噴き出していた。私の中の何かは、あっけもなく吹き飛ばされていた。いつもの通り過ぎて笑える。
私はシートベルトを外し、身を助手席に乗り出して顔面と右手をカオルの胸元に押し込んで「シャー」と叫びながら指先に力を入れると、カオルも私の頭と額の境目辺りに向かって「シャー」と叫んだその息の振動と温度を感じて、私はさらに指先にぐっと力を込めた。爪を伸ばしておけばよかったよ。