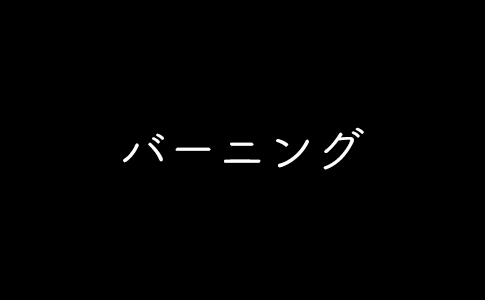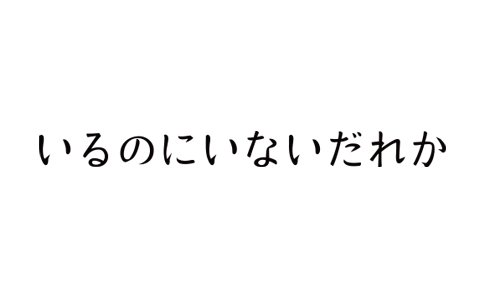本を読んでいて、その作家が紹介したり引用したりする他の本に出会うと、また読みたい本がたちまちに増えていって、すぐ、もしくは、その時を待ってから読んで、ああ、またこれも読んでみたいや―。そんなこんなで本を読み始めると、もうそこからは抜けられないループに入っている経験をしている人は少なくないと思う。
私は生活の中で本を読む時間がある程度ある。と、言うより、読むための時間を確保するようにしている。だからと言って、幼い頃から本を読むことに積極的だったわけではなく、むしろ苦手だった。文字が小さくて長い話は避けていて、例え頁数の多い本を開いたとしても、どちらかというと、その中の絵や写真、言葉からわきたつストーリーへの想像で頭の中をいっぱいにすることが楽しかったのではないかと思い返してみて思う。
こどもだと実際には体験できないような大人の世界も、情報としては知れて、勝手な想像は果てしなく広がる。今でも、声に出すと唾を飲み込むのは「ぶどう酒」だ。タイトルは思い出せないのだけど、たぶん、絵本に出てくるキツネかクマが食事の時に飲んでいたものが「ぶどう酒」だったはず。その絵本が好きだったかどうかはまた別なんだけれど、どんなにおいしいものなのだろうとゾクゾクしてた。絶対に紫色だと決めていたから、「赤ワイン」と訳されていたら、43歳になった今でも私の気持ちを放さないまでになっていたとは思えない。この「ぶどう酒」の不思議については、2つ上の兄とも共通していて度々話す。
とにかく私は、絵が大きい本がよかった。小学生になっても、読書と言えば絵本か漫画で、特に好きだった『ちびまるこちゃん』と『らんま1/2』、『海の闇 月の影』を繰り返し読んでいた記憶がある。母親が植田まさしや手塚治虫の漫画本を集めていたから、それらも読んでいた。
内容はよく分からなくても、ただ絵を追って、頁をめくるだけでもよかった。中学生になっても長編は避けて、読書感想文用の本は短いもので済ませられるように、自分で選ぶ「自由図書」で書いた。中3でさえも、さすがに絵本というわけにはいかないと思ったが、兄の本棚にあった薄くて写真の多いリチャード・バックの『かもめのジョナサン』を選んだ。結果、思いがけず感銘を受け、その後も何度も読み返す1冊となったけれども。高校生のときも、部活で熱中していたミュージカルやダンス関連の本しか読まなかった。
読むことの楽しみを感じ始めたのは、高校卒業後に米国に移って、当時親しくしていた人が本を読む人で、その人はいろんな本の話を聞かせてくれた。だから、いっしょに本を読むようになったし、尊敬している彼のことをもっと知りたくて、彼が読んだ本を通じて彼のことを知ろうとした。邪な思いも入り混じった動機からだったが、いっしょにいても、それぞれの本の世界に入って、あとで「そっちの世界はどうだった?」と、まるで旅をしてきたかのような話をすることが、安堵や興奮をふくらませ、目の前に見える風景が、それまでとちがったものになる経験が、たまらなくよかった。それからだ、本を読むことを楽しめるようになったのは。
日本への帰国を決めてからは、暮らしていたオレゴン州ポートランド市内にあったPowell’s Booksという新刊と古本を同じ棚に並べている本屋に、おそらく日本人留学生が置いていったであろう日本人作家の本があるのを見つけては、その作品に没頭した。ポップで風通しのいい空気感のカフェの喧騒の中で、太宰治や夏目漱石、芥川龍之介、宇野千代なんかを読むのは格別で、ざらっとした余韻に浸りながら本から顔を上げたときに目の前で広がる世界とのギャップに面白みを感じていた。あとは、無意識に、これからの日本での生活に向けて、準備や覚悟みたいな要素も含まれていたのかもしれない。
「なぜ本を読むのか」と訊かれると、「好き」というよりは、「必要」になっているのではないかと思う。学生の時とちがって、今は読むのも読まないのも選べる。時間制限もない。本を開くことで、誰かの語る言葉のリズムや、それによって浮き上がる景色、感情、感覚、余韻などの小さな粒が、自分の偏った見識や未知であることに問いを投げかけてくれるのが、うれしいのだと思う。文字を目で追うという一定のリズムの眼球運動も気持ちを落ち着かせてくれるからいい。本を読むという時間自体も、静かで薄暗い場所に自分をかくまって守ってくれる。そしたら、呼吸が少し楽になって、また何とかやっていこうと顔をもたげられる。だから止められない。