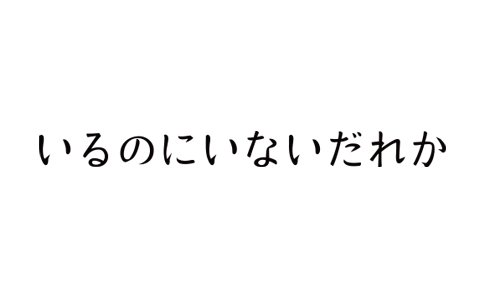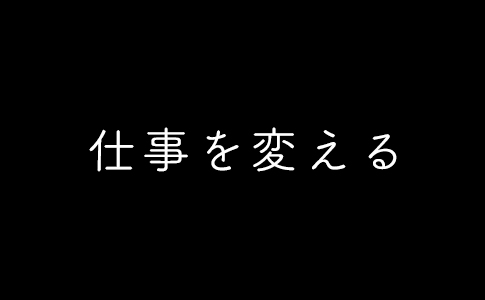カオルの長い腕で結合された塊がほどけたのは、むせてしまった私のせき払いのせいだった。
「ごめん、タマキ。あまりにも嬉しくて、つい力が入ってしまって」
私の名前まですでに知っている美しい人は、私の乱れた呼吸を手伝ってくれるかのように、ゆるやかに、丁寧に、私の背から手を放していくのがわかった。同時に、カオルも私たちに回していた腕をほどいていた。
私の横隔膜はふくらんでへこむ。ゆったりと数歩、後ろへと足を運んだ美しい人が私の目の前で瞳をうるませ、再会を喜ぶ旧友のような表情で私を見つめている。数分前まで裸で、今は服を着ている彼と向かい合って、急に自分の心臓の鼓動が速く激しくなっているのに気づく。え、なぜ。もう服は着ているじゃない。どういうこと?何に対して?明確な、まっとうな理由は浮かび上がってこない。
身体での記憶によって、勝手に身体が反応しているのか。その身体の記憶のひとつには、中学生の時に同級生に一方的に身体を触られ、床に倒されて凍てついたままでいるしかなかったときの恐怖も含まれているのだろうか。
そうだ、あの時も私は自分の目線上にあった床の綿埃をただ見ていたんだ。抵抗しようとする意識さえ失って、綿埃という小さな一点に集中していたから認知としての細かい映像や感覚、時間の記憶はない。だけど身体は覚えているのだろう、確実に明晰に。
「タマキ、タマキ」
左肩が揺さ振られる振動と徐々に大きく聞こえてくるカオルの声に、記憶の奥の方まで潜り込もうとしていた途中で今に引き戻された。
「あぁ、あぁ、うん、うん」
おかげで何とか今に電波が合ってきて、目の前のふたりがはっきりと見えてきた。私の意識がどこに行っていたのかは知らないカオルと彼は、互いに笑いかけ合いながら立っている。息の合う雰囲気からすると、このふたりは付き合っているのだろうか?ありえるね、と自分の首を絞める想像をしていたのを、吹っ飛ばしたのはカオルだった。
「紹介するよ。アキ、僕の弟」
「え、カオルの弟!?兄弟いたんだ、知らなかった」
全身を蝕んでいた緊張がさーっと引いていくのと同時に、カオルに弟がいたことも知らなかったことの寂しさが今度は拡がってきた。でも、恋人じゃなかったのは、よかった、よかった、助かったね。
「はじめまして。とは言っても、カオルからタマキの話は聞いていたから、ようやく会えたって感じなんだけどね」
カオルの1つ年下だというアキは、カオルと同じように細身で身長はアキの方が数センチ高いだろうか。アキは美しくあるための意識が高そうだ。所作も話し方もなめらか。ふたりを比べるなら、アキは太陽と月なら太陽。草と花なら花。そんな感じだ。
「アキ、お会いできて嬉しいです。先ほどのパフォーマンス、見入ってしまいました。最初はちょっと驚いたけど」
「ありがとう。気に入ってもらえたのならよかった。これからも、どんどん着ちゃう」
語尾にハートマークが付いてしまっているかのようなアキの応答が、私はたちまちに好きになった。
「きっとふたりは合うような気がしてたんだ。アキが今夜ここでパフォーマンスをすると聞いて、これはふたりを会わせるいいタイミングだと思ってね」
自慢気味に言ったカオルのその表情のかわいさも見逃さなかった私はさすがである。
それから私たちは、たわいもない世間話をして、後に今夜のオープンマイクの他のパフォーマーの話題になると、とたんに私は「白い彼女」の所在に意識が集中し、部屋内を見渡した。いない、いない。先ほどまで彼女が座っていた丸椅子も空になっている。
「ねえ、詩を読んだ全身白い装いの人、カオルやアキは知っているの?なんか、印象に残ってて」
「そうねえ。彼女は毎回ではないけど、時々来て、自作の詩を読んで、いつの間にかいなくなってる。名前も知らないし、話したこともないから、彼女のことはよく知らないけど、彼女が作る詩は独特で余計なものがないのよね。だから、聞く人の心を打つんだろうな。彼女の詩を目当てに、ここに来る人もいるくらいだから」
そうアキが応えてくれたのと同時に、会が終わった和やかな雰囲気の談笑する人たちの合間をすり抜けながら私は彼女を探した。もういないのか。
私はオレンジ色の光の中から玄関をくぐって、来た時に上った3段のコンクリートの階段を、一気に飛び降りてその勢いのまま加速したスピードで道路へ向かう。立ち止まった足元から続いている歩道線上の左右を凝視した。今が何時かはわからないけれど、もう夜も遅いはずだ。いくつかの家の窓が明るくなっているだけだ。静まりかえった住宅街の中で存在感を現す等間隔に続いている街灯のふもとや路肩に停めてあるすべての車の中を、ひとつずつ辿るが、彼女の白い姿はどこにもなかった。