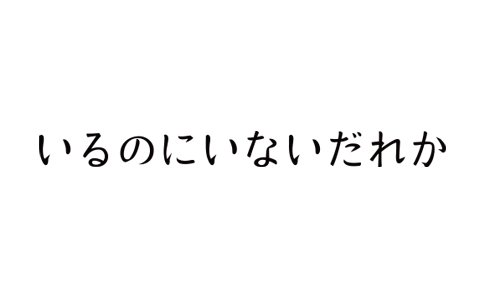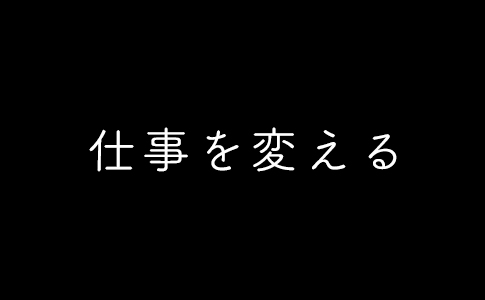奥歯と歯茎の溝に残っているチョコレートとスパイスの香りを舌でかきだしながら、カオルのナビのままに私は夜の街中を車で進んだ。対向車のライトや街灯がフロントガラスにあたった瞬間に見えるホームズの足跡は、白く光るそのたびに私はそれを上目づかいで確認する。ある、ちゃんとある、って。
「あ、きっとあそこだね、ほら」
彼は静まりかえった住宅街の中で、玄関のドアが開いたままの、そこからオレンジ色の光が流れ出ている一軒家の方を指さしながら、やや興奮気味に言った。
「了解」
私はそう独り言のように呟いて、スピードをゆっくり落とし、車を路肩に寄せた。
「さあ、時間だよ、タマキ、行こっか」
「カオルの誰か知り合いでも今夜のオープンマイクにでるの?」
彼は、いつものように口をつぐんだまま口角を上げて、私の目を一瞬見て、さっと車から降りて、オレンジ色の明かりに向かってふわりと行ってしまった。私は慌ててないフリをして慌てて追いかけた。彼の背に向かって「ずるい」と息の矢を吹き飛ばした。刺され。
玄関前のポーチのコンクリートの階段を3段上がり、玄関に入るとすでに人が集まっていて、そのほとんどは奥の部屋にいるらしかった。カオルはその奥の部屋へと向かってぐいぐいと進んでいくから私も後についた。たどり着いた部屋は、ごく普通のリビングルームだ。部屋の真ん中の壁際では、すでに全身真っ白な姿の人がマイクに向かって、詩を読んでいる。それを囲むように、3人掛け用のソファや、どこからか寄せ集めたであろう椅子に、人がすでに座っていた。彼と私も、入ってすぐの2人掛け用の籐の椅子にひとまず腰を落とした。
詩を読む人は白いパーカーのフードがまるでベールのようで、少し見えた前髪は水色だった。薄暗いのもあるかもしれないが、表情が見えない。独特なリズムで言葉をぽつ、ぽつ、と語る。いや、語るというより、ただ置く、と言った方が近いのかもしれない。骨格やその声から、おそらく女性だろう。彼女の声は、かもしだす暗澹たる空気とは異なって、澄んでいて柔らかい、そして小さい。やがて詩は加速し、彼女が合間に突き出す怒りや祈りの入り混ざったような両腕の右の袖口から、ちらっ、ちらっと見える腕の内側の数えきれないほどの傷から目が離せなかった。リスカを常用しているのだろう。古いものと新しいものが重なっている。おそろいだね、と私は親しみをこめて右頬を彼女に向けた。
気がついたときには彼女の詩は終わっていて、彼女の詩の内容を振り返ろうしたが、記憶として処理されていなかったようで、そもそも思い出せない。拍手の中、彼女は部屋の角にある木製の丸椅子に静かに座った。さらに気がついたのは、となりにいたはずのカオルがいないことだ。横目で不在を受け入れ、大きく息を吸って、細く長く息を吐く。
それから、自作の曲をギターで弾き語る人、『スッタニパータ』の「犀の角」を朗読する人、20年前の自分自身宛ての手紙を読んだら嗚咽して途中で止めた人、けん玉をしながらラップをきざむ人などがいたのだが、私はそれぞれの目の前の出来事より、その人の経緯や背景を組み立ててしてしまう。自動操縦的にやってしまう。だから結局、今目の前がぼやけてしまう。
しばらくマイクの前があいたままになり、もう今夜のオープンマイクはお開きなのかと、周囲を見渡してカオルを探していたら、隣の部屋からまっすぐにマイクのある箇所へ向かって歩く人がいた。その人はマイクの近くに立つと右腕に抱えていた麻布の包みを床に置いて広げた。なんだろう。そこには衣服がきれいに重なっていた。彼は服を着ていない、裸だ。そして、ゆっくりゆっくりと黒のボクサーパンツ、白地のネイビーライン靴下、黒のデニムのパンツ、ライトイエローの無地のTシャツを身につけた。ただそれだけだった。
だが、彼のしなやかで迷いのない動作のうつくしさに、私の意識すべてがもっていかれてしまった。え、なにこれ。呆然としている私に、衣服を身に着けたばかりの彼が、先ほどと同じように、まっすぐに、私に向かって歩いてくるではないか。彼は私が見えていないのかもしれないと咄嗟に思い、移動しようと身に力を入れたが、逃れる前に彼は右手を私の背中にまわし、すくい上げるようにして、ぐっと彼の胸元へ引き寄せた。猫背気味の私の背と所在に困った両腕は状況がつかめず、中腰の体勢のまま、てんぱる。ただ、背中にある彼の手の感触にエロさはゼロで、やさしかった。そして彼の右のむき出しの鎖骨あたりに押し当てられた私の鼻孔は、なつかしさを感じていた。
「やっと会えた」と彼は言ったから、やはりどこかで会ったことがあったのだろうか、と記憶の頁を猛スピードでめくりまくる。彼の肩で半分はせまくなった視界をキョロキョロしていると、こちらを見ているカオルに焦点が合った。反射的に困ったのは私だけで、満面の笑みを浮かべたカオルは私たちの真横に立ち、長い両腕を私たちにまわしたおかげで、私の背はさらに押し上げられた。くの字のままの私の両太ももは、ぴくぴく震え始めていた。ホワイトセージの香りがした。