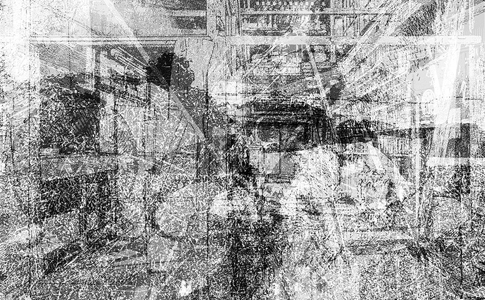「そろそろ、行ってみようと思います」
私はコーヒーの最後の一口をゆっくりと飲み干し、カップをテーブルに置いた。
「駅へ行く予定でしたよね。こちらの窓から出ていただくと道に出ますので、右の方へ行ってください。駅までは15分くらいで行けると思います」
男性は私の後ろの窓を指して、柔らかい口調で教えてくれた。
「コーヒーごちそうさまでした。ありがとうございました」
軽くお辞儀をして、席を立った。
アルミサッシの取っ手に手をかけ、サーっとスライドさせると、留まっていた空気が一気に外へと吹き出した。同時に、充満していたコーヒーの香りが吹き抜ける風に乗って、私の顔をかすめるように抜けていくのがわかった。私は背中を押されている気分で、軽快に敷居をまたいで外へと足を踏み出した。
外に出ると、柔らかい日差しで明るく照らされた庭が広がっていて、足元から延びる出入り口へのアプローチが道路まで伸びている。舗装されたコンクリートで固められていたが、表面は丸い模様で装飾されていた。その真ん中には植木鉢が埋め込まれていて、紫色の花を咲かせたラベンダーが植えられている。さわやかな香りに惹かれて1匹のミツバチが花の周りを飛んでいた。

「植木鉢舗装だよ」
後ろから声が聞こえる。振り向くと、男性がこちらを見て何やら話しをしたそうにしている。
「自分でつくったんですか」
私は話を誘導するように問いかけた。
「庭に落ちていた植木鉢を集めて、中にモルタルを流して並べてあるんですよ。大きさが違うから平らにするのが難しくて、凸凹してるでしょ。並べるのが大変だったよ」
確かに手づくりしたことは一目でわかるが、見たことのないアプローチの舗装と、その脇に植えられた名前の知らない植物たちが、味わいのある庭を彩っていた。その中の1つを指さして、男性に聞いてみた。
「この植物は、なんていう名前ですか」
「それは、ヒューケラ。色違いがたくさんあって、赤いのはドルチェ。黄緑がレモンシュプリーム、オレンジ色がトパーズジャズ、白っぽいのがオブシディアン、っていう名前で、まだ他にもあるけど、覚えられないですね。寒さにも強いから、冬越しできる植物をたくさん植えているんですよ。その隣は、ユーフォルビアで、多肉植物に似ていて、葉っぱが特徴的な植物です。これも種類がたくさんあって、サボテンみたいな種類もあるんですよ。それと、そこの鉢はハーブの仲間でオレガノとタイムです。冬には枯れてしまうけど、夏になると急に成長するので、初めは少なめに植えておくといいですよ。その奥の白い花はリッピア。日本語ではヒメイワダレソウという名前で呼ばれていて、グランドカバーで植えています。繁殖力が強いから他の植物とは離して植えた方がいいみたいです」
「初めて聞く名前ばかりです。覚えられないけど、教えていただきありがとうございます」
お礼を言って、いったん話を止めようとするが、男性は構わず話を続けた。
「その奥の植物はグレビレア・ラニゲラといって、ごつい見た目ですけど、かわいい赤い花が咲きます。あっちのススキみたいなやつはパンパスグラスといって、秋にはピンク色のふわふわした実がつくので、ピンクフェザーという名前がついています。今年植えたので、まだ見られていないですが楽しみです」
先ほど黙ってコーヒーを飲んでいた人とは思えないほど饒舌に、庭の植物についての説明をしてくれた。思っていた以上に知らない名前が続く。しかし、外国人のような名前やその見た目と特徴に、知らぬうちに興味を持って話を聞いていることに気が付いた。

「あっちの斜面に植えたのは白い葉っぱのグランドカバーでディコンドラです。松の木の下にはオレンジ色の花が咲くトリトマが植えられています。大きくなると迫力が出るので、数年後が楽しみな植物です」
ドラフト会議で獲得した若手選手を見守るような言い方だと思った。
「植物にもそれぞれ個性や相性が合って、環境や機能によって植える場所を決めています。それと、全体のバランスも考えないと、美しい庭にはならないみたいです」
「なるほど、面白いですね」
そう考えると、見慣れない個性的な外国産の植物は、外国人の助っ人選手を獲得することにも似ている。
ここは庭というグラウンドで、切磋琢磨して競い合いながら成長する1つのチームのような場所なのかもしれない。中には、淘汰され消えてしまう個体もいるであろう。枯れて戦力外になる植物もあるに違いない。庭を管理するこの男性は、差し詰め監督でありチームオーナーといったところだ。いい庭をつくるには、お店に並べられた商品を見て、気に入った個体を植えるだけではだめで、個性を生かしたバランスの良い配置が大事なのだ。
そして、植物も人間や動物と同じで栄養がないと生きていけない。愛情をもって見守り育てることで、やがて実り、チームの一員として輝くのだ。
これまでそこにいた植物たちが、力強くこちらの様子をうかがっているように思えた。不思議と外の景色が一段と生き生きして見えるのだった。