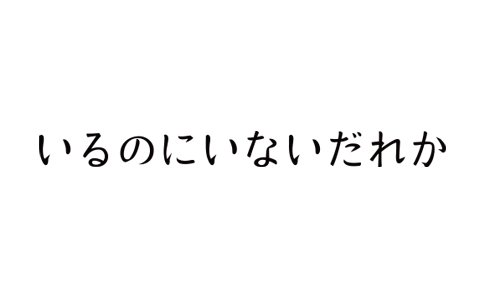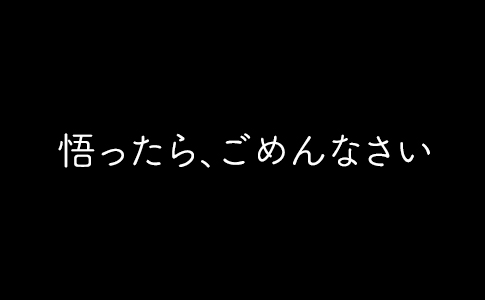この瞬間を待っていた。視界がだんだんと薄ぼやけてきて、常套である「走馬灯」のように、情報処理され、いつかの記憶が引っ張り出されるこの時。私の人生のハイライト。見開いた目の前でカラカラと音を立てて繰り広げられたのは、幼い頃に愛されていると感じられた唯一の瞬間や、自分の存在意義が縁どられた職場での役職の交付のあった瞬間の映像、そこへ一筋の涙が流れれば理想的だったのだが、現実には目線より5mm程の高さしか離れていない位置に広がっているヨガマットと、その先の床の上の埃だけだった。
もう限界、まばたき。
大きく息を吸うのと合わせて、私は握りしめていた両手をほどき、両掌でヨガマットを押して上半身を鶏が目を覚ましたような機敏な動きで起こした。私であると感じていた「ハロルド」の真似を本気ですることで、私はもう一度息を吹き返す。吐いた息を感じながら、右頬にチリチリとした痛みがあることがわかった。
よいしょと立ち上がって向かった洗面所の鏡に映っている私の右頬には今まで累積してきた跡を打ち消すかのような赤が付いていた。数回繰り返した直の床上だと、もろクソ痛かったし、だからといって、ふかふかの布団の上では、なんとなく癪だから、中庸であろうヨガマットを選択したのに、結局、摩擦にやられてしまった結果に、少し落胆した。考えが甘いんだよ、鏡に映る私に言った。
部屋に戻って、アレと大量に流れたであろう体液をヨガマットにくるんで、筒状になったマットを壁際の定位置に戻した。右頬が、またピリッとしたけれど、気づいていないフリをして無反応のまま、レトロ刺繍がほどこされたボヘミアン風の白いブラウスとデニムを着た。毛穴が目立たない程度のファンデーションと、マスカラ、ローズの香りのピンクベージュカラーのリップクリームをつけると、気持ちが上がる。鏡に向かって笑う練習もしてみた。それなりに悪くはないと思えた。
約束の時間に到着すると、あたかも私が今夜の約束に執着していたかのようだから、一旦、近くのコンビニの駐車場に車を停め、ルームミラーに映る自分の目の辺りだけを見た。少し背筋を伸ばして顔下半分を映す。コンビニからの蛍光灯が、線や穴を立体的にするから現実を知る。
約束の時間を10分程過ぎてから、カオルの家の前に車を横付けし、呼び出しベルを3度鳴らした。彼は携帯電話で話しながら開けたドアを押さえ、私に部屋に入るようにとジェスチャーをした。部屋の中は、植物を燻した香りが充満していて、私の鼻下からしていたローズの香りと交じり合って、何だかとてもいい気分になっていた。電話を終えた彼は、いつもの嬉々とした表情で私の近くへ歩み寄ってきた。
「いい香りがするけど、なんだろ」
「でしょ、ホワイトセージを燻したんだ」
と言って、彼は部屋の角に置かれたホワイトセージの灰が残されたステンレス製と思われる小さなボウルの方を指さした。私はその方向を向いて、吹けば舞い散ってしまいそうな灰に目線をやった。
「タマキ、その傷、何?赤くなってるけど」
うっかり右頬を突き出してしまった。不覚にも気づかれてしまったハラキリたこを彼はしげしげと見ている。隠すのも、気のせいだと誤魔化すのも、なんとなく私の中で拒まれた。
「そうそ、これね…好きな映画の主人公がハラキリをするシーンがあるのだけど、その真似をしてたら、擦っちゃって…いやでも、見た目よりそんなに痛くないから大丈夫だよ」
私はヘラヘラ笑いながら、彼の正面に立っているのが我慢ならなくなって、灰の入ったボウルの方へ軽やかに足を運び、彼に背を向けた。あれ、何の返答もないのだけど?振り返ると、その場で突っ立ったままの彼が眉毛と肩を八の字にして私を見つめている。この擦り傷を、私のたこを、行為を憐れんで心配しているのだろうかと少しの期待がふくらんだ。彼が言った。
「パーフェクト」
「え?」
「あの映画のハラキリを実演できるなんて、さすがだよ。誰にでもできることじゃない」
目を爛々と輝かす彼を目の前に、傷の痛みを慰めてほしいと思ってしまった自分の幼稚さが滑稽に思えて、薄笑いしか返せなかった。
コバルトブルーの無地のTシャツにライトグレーのパーカー、黒のデニムのパンツ姿の彼は、出発間際に「忘れ物」と言い、台所の棚から何やら紙包みをつかみ、パーカーのぽっけにしまった。もう真っ暗な夜の中に飛び出して、彼は助手席に、私は運転席に乗り込み、エンジンをかける。
「ちょっと」と彼が言ったかと思うと、先ほどしまった紙包みをぽっけから取り出した。チョコレートだった。一口大に彼がチョコレートをおっかき、無言のまま彼と私はひとつずつつまみ、互いの目から目を離さず、互いの口の中へ茶色の欠片をゆっくりゆっくり差し込んだ。溶けていく。スパイスの香りが強烈だ。私のたこに刺激が過ぎるのではないだろうか。反射的に私は目を見開くと、
「大丈夫、オーガニックだから」
と応答があった。