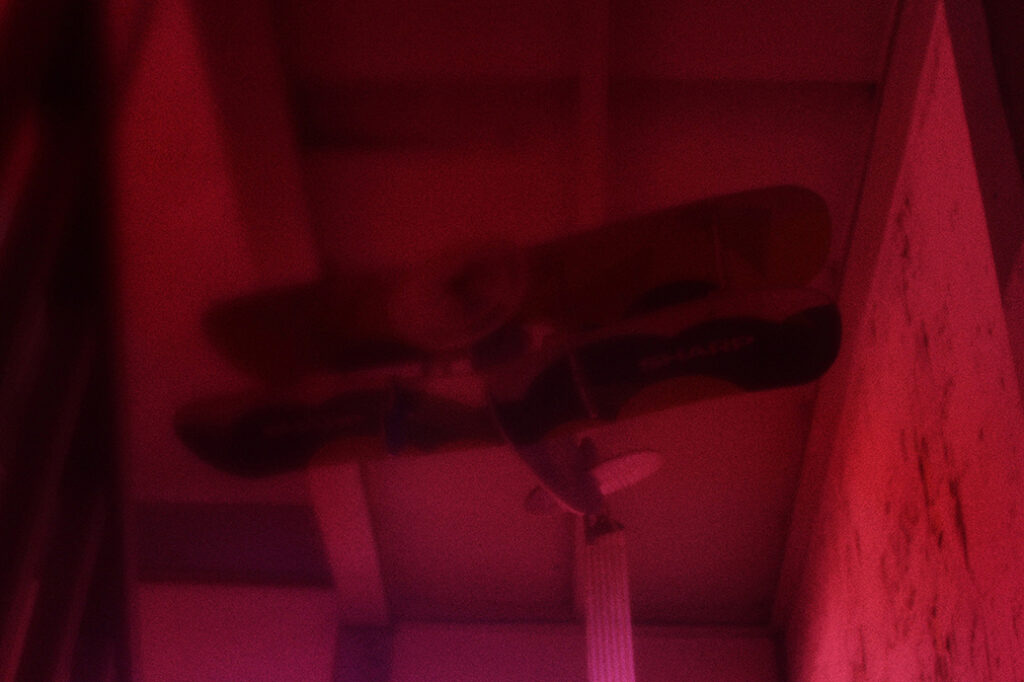
「しゃべる時は」
と男が言う。
「しゃべる時は、この紙に書いてください」
指し示されるのはキャビネットの上に厚く積まれた手のひらサイズの正方形の紙切れ。切り分けたガトーインビジブルのように、そそり立つ断面は美しい。
「つまり、声を出してはいけないと言うことですか」
「平たくいえば」
そう言うことですと男は。
奇妙な場所だと、彼は思う。見上げると自分の背丈のおよそ七倍ほどもある四方の壁が、上から下まで色のないカーテンで覆われている。対角線の位置にある出入り口から吹き込む風で、カーテンはゆらゆらと揺れ続けている。空飛ぶ部屋というものはこんな感じに違いない。部屋全体が、風をまるくはらんでいる。
心地よい、と気だるい、の中間で脳みそを揺さぶられながら、まるで大きな揺籠のようだと、彼は身震いする。揺籠が安全な場所だという認識が、彼にはできないでいる。
カーテンの裾にはパンチで穴の開けられた紙切れが、丁寧にピンで停められているーEverest snow。
言い得て妙だ。雪のように輝くような白さが満ちるこの部屋には、その実陽光というものは髪の毛一筋ほども差し込まないのである。現実ならざる心地はそれが原因かもしれないと彼は考察する。
ときおり聞こえるのは駅のアナウンスだ、25番線から列車が発車します― パー!無意味なラッパ音に〈ファンファーレ〉。拍手ののち、回転し始める車輪の軋む音。ノイズが交じるのでわかる、ラジオかなにかだろう、極めて不快な趣味だ。
部屋の中央には回転する円盤、テーブル、もしくは巨大な石臼。上面に雑多に並べられた静物には統一性がなく、大きさもまちまちだ。花瓶、アイロン、旅行鞄、ソファ、タイヤ、窓枠に背丈が二メートルほどもある棚、エトセトラエトセトラ。それらがてんでバラバラの方向を向いて、ゆっくりと右回りに回転している。
ぬるい室内の空気が、多種の匂いにかき回されてさながら古物の香水を作り上げる蒸留装置のようである。
「それぞれに色を貼り付けるのが、あなたの仕事です。この色見本を使って」
と示されたのは腰掛けるのに具合の良さそうな紙の塊。目方で縦横高さ共に50センチほどの本、のようなもの。表紙は薄い金属でできていて、色見本、と刻印がある。真鍮のリングでまとめられている。開いた様子は、大きなアコーディオンを想像してもらうと良いだろう。
この岩のような塊を繰りながらの作業はそうとう骨が折れるに違いない。めまいを感じて彼は内心よろめく。実際、わずかによろめいてみせる。〈ファンファーレ〉、拍手。この部屋に来て13回目の発車。
部屋をぐるり見渡し、目を引いたのは真っ赤な金魚鉢。床に無造作に置かれている。
「それは備品ですから分類の必要はありません」
視線に気づいたのか、ぴしゃりと男が言いつける。備品。揺れる水。黒い粒が浮遊している。覗き込むと赤い金魚が泳いでいるではないか。鉢が赤いせいで外からは全く見えなかった。やはりどうかしている趣味である。
タグをつけるならば、drain cherry か。
「他にあなたにするべき説明はありません。くれぐれも音を立てずに、ラジオを聴き逃してはいけない」
男は金属性の物差しのような声色でそう言う、彼を見つめる青ざめた男の瞳は、沼底のように暗く、けれど安堵に満ちている。
彼は黙々と分類を続ける。
糊のついた紙に色名を記し、目立つところに貼り付け、それは運び出す人間たちによって室外のどこかへ運ばれていく。
回転する円盤の上の静物は減らない。出口とは逆の側から運び込む人間たちによって、厳かに、規則正しく補充される。
彼はずっと気になっている。
この場の安全性や今後起こる何かについて、なんの説明も受けなかったことに関してではない。そんなものは、誰にも説明できないと知っているからだ。地と天が返ってしまえば、助かるのは宙に釣られた窓拭き掃除夫くらいのものだ。
ぽちゃりと水音が、その微かな音で彼の首筋は粟立ち、意識を右と左にピンとはられる心地がする。
俺を見ているに違いない、
背後にあるはずの硝子性のドレンチェリー。その中の外側からは不可視な金魚。赤く染まった水、浮遊する水晶体。
金魚は赤い水に紛れる。わずかな水流でしか、その身体をさとらせない。
根拠もなく、知っているのだろう、と思う。お前は知っているのだろうと。浅はかで、短絡的な、妄想をする。
一際大きな拍手が彼を物思いから引き戻す。電車は大量の人々を乗せて発車する。最終便はいつ出るのだろう。今は一体何時なのだろう、いつまでここで、どうして、
(ここの奴らは、こんなにも自分たちが救われることを信じて疑わないのだろう!)
彼は色見本を捲る手をとめる。かたわらのガトーインビジブルから一枚とって、手にした万年筆を走らせる。
whyーどうしてだ。
何の何故を示しているのか、彼にもわからない。けれどそれ以外の言葉も出てこない。自分が手のかかる記憶喪失の人間になったかのような感情に襲われる。俺は何かを忘れているー忘れていれば、よかったのに。
彼は運び出す人間の1人に紙切れを手渡す。すると、すぐに突き返される。紙にはこう書いてある。
「ものはあるべき場所に。色もあるべき場所に」
立つ鳥跡を濁さずと言うわけか。わざわざ次の住民のために綺麗にお掃除とはなんて物分かりのいい。
彼は受け取ったメモの端にgâteau invisible と殴り書きし、運び出す人間に手渡す。紙は受け取った人間の手によってグシャリと握りつぶされ、背広のポケットに捩じ込まれる。
満ちるのは焦燥感。
歓声、高らかな指笛と、拍手喝采、人々のヒール音。それに混じるノイズ、たまに入る列車の時刻アナウンスがハウリングのせいで破裂する。プアアアアンンンン!
繰り返し、繰り返し。
不意に彼は、足元の奇妙な感覚に気づく。靴紐にかぶるほどに水浸しな床に。
運び込む人間と運び出す人間の足元で、細かな飛沫が赤く跳ね返っている。
赤く?
drain cherry。
振り返る。髪を振り乱して振り返る。彼の残像が7つ空間に残る。
赤い金魚鉢から、薄赤い水が流れ出している。溢れている。ビー玉ほどの大きさの黒曜石が、ゆらゆらと揺れている。
水は事象を覆う。全ての分類した色彩は、赤に回帰する。赤に寝返る。
四方のカーテンが、液体を吸って重みに沈黙する。たまに水流に引っ張られ、ハリボテの景色のようにぐらぐらと横揺れする。なんだ、これは。どうしてこんなにも、何かが終わりそうなんだ。
終わりそうなんじゃない、もうすぐ終わるのである。
スピーカーからは時折悲鳴の混じった喧騒が聞こえる。
最終便!最終便!最終便まであと4本!
拍手はもうならない。〈ファンファーレ〉も。怒号が飛び交い、混沌とした音声の中で彼は、握りしめていた鉄筆を水中に叩きつける。Galaxyと書いた紙が間もなく水流に。赤い水は膝下まで来ている。
人間たちを、いや、もう人間かどうかはどうでも良い、歩く葦を押し除け、鉄板のように重いカーテンをめくり、運び出す人間が出ていく戸口をくぐる時、背後で小さく音がする。何かが弾ける音がする。
ドレンチェリーが、真っ二つに割れている。





