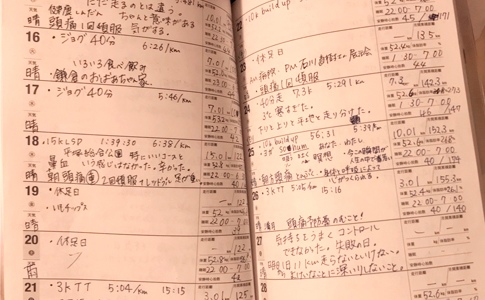5月も後半になると、家の中ではタンクトップにショートパンツ、裸足で過ごせる快適な気温になってきた。
身につけるものにはやっと年々頓着が無くなってきて、白Tや開襟シャツにショートパンツ、5本指ソックスに足に合ったシューズ(今はずっとビルケンシュトック)、きれいな石のついたネックレスやピアスがあれば十分、という気持ちになっている。
肩がこらず、布巾のように毎日洗ってバリっと乾いて、さっと着られるような服の繰り返しでいい。
そんなメンズライクな落としどころだったのか、と41歳にして気付く(そういえば自分がかっこいいなぁとずっと憧れていたのは、白シャツと黒パンツ以外目にしたことのないエレファントカシマシの宮本さんや、どんな大きなミュージアムで展覧会をしようとも、授賞式でもいつもロックTに細身のパンツ姿の画家の奈良美智さんだったりした)。
20歳の頃に、興味の向かなかった成人式の着物は着なかったけれど(以前も書いたが式も出ていない)代わりに福島県の山葡萄の蔓で編んだ籠を自分で購入した。
以来その籠に合う身なりを、ずっとずっと模索していた。
10代の頃読んでいたファッション雑誌が『装苑』と『Zipper』で、ルーズソックス全盛の中ヴィヴィアン・ウェストウッドのソックスを履くような、すでに主流から外れてはいたのだけれど、その後『Olive』の世界感が好きになったり『GINZA』が発刊し、好みのアイテムを切り抜いては自分のイラストと合わせたりして遊んでいて、ファッションイラストレーターに憧れたりもしていた。
働き始めて好きな人ができれば、ヒールの靴を履いたり髪を巻いてみたり「それらしい」格好もするのだけれど、それと山葡萄の籠はどうしたって似合わないし、夕方には脚が痛くてじんじんしてくる。結局、せっかく塗ったネイルだって窮屈に感じてすぐに落としてしまうのだった。

そもそもなぜ山葡萄の籠に興味を持ったのかというと、高校生の頃、知人のリサイクルショップでアルバイトをしていて、その知人が骨董の知識や面白さを教えてくれた。リサイクル品の買い付けにたまに一緒についていき、ほとんどは使わなくなった洗濯機や不用品の回収なのだけれど、たまにオールドノリタケのコーヒーカップセットなどが出されることもあり、そういうものの見方だとか蘊蓄を話してくれた。
その知人は「親から引き継いだリサイクル店だけれど、本当は骨董をやりたいんだ」とよく夢を語っていた(今ではちゃんと夢を叶えて、北欧家具や食器を専門にヴィンテージやアンティークをかなり大きな規模で扱っている)。
骨董は身銭を切らないとわかるようにならないと教わり、明治に作られた縦縞模様の蕎麦猪口を買った。初めて買った骨董品だった。
それから骨董市や蚤の市、鎌倉や下北沢のアンティークショップにも足を運ぶようになり、独自に器の世界にのめり込んでいく中で「民藝」と出会うことになる。
民藝とは、名もない職人たちが庶民の生活のために作った工芸品のことであり、民藝品には「簡素で飾らない健康的な美しさ」があると柳宗悦は説いている。その毎日使うものに美を見いだす視点に、私はずっと共感し憧れ続けている。
そういった中で、たまたま都内のデパートの物産展のようなところで出会った、民藝の書籍の中でしか見たことの無かった山葡萄の籠を、清水の舞台から飛び降りる思いで購入したのだと思う。
そこからおよそ20年以上経ち、今使っている器のほとんどが自分好みの民藝のものや、ヨーロッパの古いものだ。
どこの窯くらいしかわからない。
初めて骨董を教わってから、しばらくはたくさん買っては失敗し手放し、ここ10年くらいはテーブル周りのものは自分の好き、と相違なく価格に関わらず、すぐに選択することができるようになった。
それには、選びとった対象のどこに自分が惹かれているのかを、静かに毎回ようく、よーーーく細部まで観察し続けることだと思う。心にちゃんと従っていると、自然と違うものは選ばなくなる。
ただ、服だけはなかなかいつまでも本当の自分の好き、を選びとることが困難で心から選んだ籠と似合う服を決められずにいた。
テーブル周りや自分の部屋に掛ける絵は気持ちと違わず選べるのに、服を決められないのは何故か。
誰の視線も介入しない部屋の中の食器や絵画と違い、他者の視点が混ざり自分の感覚が濁ってしまう率が、断然、外に出る際身につける服装には高くなってしまっていたからだ。
近年、様々な生活や内面の変化があり、今初めて他者の視点を気にせずに、好きな服を身につけられるようになっているかもしれない。例の山葡萄の籠とも今の自分の内側とも、擦り合ってきていると感じる。
他者やメディアの視点を切り離し、気に入りの服やアクセサリーを毎日身につけられるということは、きっともっと自分の人生がご機嫌になっていく、ということだと思っている。